世界の文明を支えた雑穀!健康志向で見直される雑穀のメリットとは
- g-veggie

- 2025年9月5日
- 読了時間: 10分

健康ブームの中で脚光を浴びている雑穀。
雑穀は体にいいというイメージがありますが、同時に美味しく食べるのが難しいと思っている方も多いことでしょう。
雑穀とは具体的にどんな食材を指すのでしょうか? また、栄養面におけるメリットが多いといわれる雑穀、実際にはどんな効能が期待できるのでしょうか?
今日は雑穀のメリットや食べ方について、詳しく解説いたします。
雑穀とはなに?その定義は
雑穀という言葉を耳にしても、具体的なイメージがわかないというのが実情です。
まずは雑穀の定義についてみていきましょう。
時代や地域によって変化する雑穀の定義
人間が農耕を始めたのは、およそ1万年前といわれています。(※1)
人間がその種子などを食べる農作物を、総称して「穀物」といいます。(※2)
穀物には、主食とする主穀とそれ以外の雑穀に大別されます。
主穀の代表が、私たちの食生活になくてはならない米です。そのほか、麦も主穀とされています。
一方雑穀は、アワ、ヒエ、キビ、ライムギ、エンバク、ハトムギなどがあります。
日本では雑穀とされているモロコシは、アメリア大陸では主穀の扱いです。日本の主穀である米は逆に、アメリカでは雑穀に属します。(※3)
このように、雑穀の定義は地域や時代によっても変化するのです。
いずれにしても、歴史の中で人間の食生活に重要な役割を果たしてきたことでは共通しています。
雑穀が少ないのはなぜ?
米などの主穀に比べると、現代社会において雑穀を食べる機会はそれほど多くありません。
その理由はなんでしょうか。
雑穀はそもそも、安定した農作物の収穫ができなかった場合に、主穀を支える二次的な穀物という概念がありました。主穀が不作であった場合は、代用として食べられてきたのが雑穀なのです。
現在は農業技術も向上し、主穀は充分な供給があります。そのため、ごく自然に雑穀は姿を消していく運命にあったわけです。(※3)
しかし、生活習慣病等の現代病が社会問題となる中で、雑穀が持つメリットが脚光を浴びるようになりました。(※1)
すでに姿を消しつつあったさまざまな雑穀が、再び栽培されて市場に出るようになったのです。

代表的な雑穀(世界編・日本編)
雑穀の種類は非常に多く、世界各地でそれぞれの気候に合った雑穀が栽培されてきました。
たとえば江戸時代の南部藩(岩手県)の記録には、アワだけで380品種が登録されているそうです。(※4)
世界のあちこちで収穫され人々の生活を支えてきた雑穀について、簡単に説明いたしましょう。
日本の雑穀
日本の主食は米ですが、稲が日本に伝わったのはおよそ3000年前といわれています。
それ以前から、日本人はヒエやエゴマなどの雑穀を食べていたことが研究から判明しています。
とくにアワ、ヒエ、キビが日本ではよく食べられてきた雑穀です。
アワがよく採れた阿波の国(徳島県)、ヒエをよく食べていた閉伊の国(岩手県)、キビが多かった吉備の国(岡山県)など、地域の名称も雑穀にちなんでいるという説もあるのだとか。(※5)
これらの雑穀は、1940年代までは米に混ぜて雑穀ご飯として食べていました。


アジアの雑穀
アジアでよく食べられていた雑穀は、日本と同様にアワやキビでした。
またインドには、サマイやコドラといった穀物も多く、インドビエなどの固有種も栽培されています。
アフリカの雑穀
雑穀は乾燥する地域でも長期保存ができる貴重な食材でした。
灼熱の大地アフリカでは、モロコシという雑穀がよく食べられてきました。これはアジアに伝わって高粱という名で知られるようになります。
また指の形をしていることからフィンガーミレットの別称を持つシコクビエも、アフリカの食を支えてきた雑穀です。(※1)
中南米の雑穀
中南米は、マヤ文明をはじめとする優れた文明が興隆した大地です。
それらの文明を支えた雑穀には、トウモロコシやアマランサス、そして現在はスーパーフードとして知られるキヌアなどがあげられます。
いずれも紀元前の時代から食べられていた雑穀ですが、20世紀になって姿を消した雑穀も多いのだとか。(※1)

ヨーロッパの雑穀
パンを作るための小麦がメジャーであったヨーロッパですが、アジアからキビやアワが伝わり、人々のお腹を満たしていました。また北欧では、ライムギや大麦なども盛んに栽培されていたと伝えられています。(※1)
世界各地に興隆した文明を支えてきた雑穀ですが、アジアの稲、南米のトウモロコシ、ヨーロッパの小麦などの画一栽培が普及してからは、栽培が衰退してしまったわけです。

さまざまな雑穀のメリット
近年、健康志向の中で注目されることが多くなった雑穀。
雑穀にはどんなメリットがあるのでしょうか?雑穀を食べるメリットを簡単に解説します。
雑穀は食物繊維が豊富!ダイエット効果も抜群
一般的に、雑穀は白米よりも豊富な食物繊維を有しています。
日本の代表的な雑穀、アワやヒエと白米の食物繊維量を比べてみましょう。(※6・7・8)
100g当たりの食物繊維含有量
白米 1.5g
アワ 3.3g
ヒエ 4.3g
日本人の食物繊維摂取量は、年々減少傾向にあります。
厚生労働省では、成人女性ならば1日最低でも18g以上の摂取を推奨していますが、現在の食生活ではその数値をカバーすることは困難。
でも雑穀を食べれば、食物繊維を豊富に取り入れることができるのです。
なぜ食物繊維の摂取が必要なのでしょうか?
それは、こちらのような理由によります。(※9)
腸内環境を整え便通をよくする
ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を増やす
心筋梗塞や脳卒中などの予防につながる
乳がんや胃がんなどの発症率を下げる
コレステロール値を下げる
つまり、健康にも美容にも多大な寄与をしてくれるもの、それが食物繊維というわけですね。
咀嚼する回数府が増えて満腹感が得られる!
雑穀は噛み応えのある食感のものが多く、自然噛む回数が多くなります。
実はこの咀嚼の数、肥満とも深い関係があるのをご存じでしょうか。
厚生労働省のサイトには、早食いをする人は肥満になる傾向が高いことが報告されています。(※10)
そう、もぐもぐとよく噛んで食べる必要がある雑穀は、肥満予防に寄与する可能性が高いのです。雑穀を活用することで、ダイエットができる可能性もあり。
さまざまな雑穀をしっかりと噛んで、満腹感を感じてみてください。
種類によって多様な食感を楽しめる!
雑穀の種類はとても多く、それぞれの食感も異なります。
たとえば大麦ならばモチモチとした味わいが魅力的ですし、キヌアならばプチっとした歯触りが新鮮です。市販されているミックスの雑穀ならば、煮込んでいくととろみがつくことも。
つまり雑穀は、味わいが単一ではないため、飽きることなく食べることができるわけです。
地中海食の一端を食卓に持ち込める
ユネスコの無形文化財となっている地中海食は、肉や魚の量が少なく、雑穀をたくさん食べるという特徴があります。
これまでの研究では、雑穀が多い地中海食を意識して食べることで、生活習慣病を持つ人たちの症状が改善したという報告がされています。(※12)
またイタリア保健省によれば、雑穀を支柱とする地中海食はサステナブルの観点でも健全な食のスタイルであることが明記されています。(※13)
上手に食べれば、おしゃれな地中海の食事を食卓に乗せることができるでしょう。

雑穀にデメリットはある?
さまざまなメリットがある雑穀ですが、デメリットはあるのでしょうか?
食べる際に気を付ける点も含めて、解説します。
消化に時間がかかることもある
雑穀はよく噛んで食べる必要がありますが、いいかえれば消化に時間がかかる食材なのです。
そのため、乳幼児に雑穀を食べさせることは控えたほうがよいと言われています。(※14)
また、高齢者が食べる場合も、調理前の浸水時間を長くするなどの工夫をすると消化しやすくなります。(※14)
食感や香りに慣れない
雑穀の数は多種多様。
普段食べ慣れていない雑穀にトライしても、香りにびっくりしたり、食感がイマイチと感じることもあるかもしれません。
また、調理法に躊躇してしまうという方も多いことでしょう。
こうしたデメリットは、雑穀を少しずつ食生活に取り入れていくことで解決することができます。
雑穀を美味しく食べる工夫を!
あまり馴染みのない雑穀。調理方法に頭を悩ませてしまうこともあります。
雑穀はどんな風に料理したら美味しく食べることができるのでしょうか?
いくつかの例を紹介します。
基本の調理法はシンプル!
雑穀の基本の調理法はごくシンプル。
「茹でる」「炊く」「蒸す」という3つの方法で、大半の雑穀は食べられるようになります。
雑穀によっては、基本の調理をした後に冷凍しておくこともできます。
主食として食べる
雑穀はお腹の持ちがいいので、主食として食べるとよいでしょう。
白いお米と混ぜて炊いてもいいですし、きのこやアサリなどと炊き込みご飯にしても美味しく食べることができます。
トマトやアスパラなど色のきれいな野菜を使ってリゾット風にしたり、オリーブオイルをたっぷり使ってパエリアにすると、お客様にも出せる一品になります。
スープにする
雑穀の食感が苦手という方におすすめなのが、汁物の具にする方法です。
毎日食べるお味噌汁はもちろん、ミネストローネやポタージュに入れると、苦手な食感もよいアクセントとなって美味しいと感じるかも。
夏ならばガスパチョ風に食べやすくして、雑穀で栄養補給するのも手ですね。
ソースにする
雑穀の意外な活用法、それはソースにすることです。
ヒエやアワなど、風味がイマイチと感じてしまう雑穀はソースやドレッシングにすると、日常的に摂取できます。
ハンバーグもグラタンも!子どもが喜ぶメニューに
雑穀だけを食べようとすると、子どもは見向きもしない。そんな経験を持つ方もいるのでは?
でも雑穀をハンバーグにしたりグラタンにしたり、肉団子のスープにしてしまえば、子どもたちもぺろりと食べてくれることでしょう。調理に工夫をすれば、雑穀は多くの料理に応用可能なのです。

メリットが多い雑穀を近しい存在に!
雑穀というと、貧しい時代の象徴のようなイメージを持つ方も少なくありません。
しかし現在は、栄養面やSDGsの観点からも、雑穀は世界で注目される食材になりました。それに呼応するようにレシピも増え、雑穀の使用もハードルが低くなりました。
健康や美容に大いに役立つ雑穀、ぜひ楽しく調理して美味しく食べてみてください!
【おすすめの講座】

雑穀のお買い物はこちらから⇒G-veggieマーケット
オーガニック料理教室G-veggie

G-veggieはGrain(穀物)とVeggie(野菜)を合わせた造語で、人間にとって大切な2つの食べ物を、料理の中心にして自然に寄りそった生活をしていきたいという意味を込めました。
自然の生命エネルギーあふれる「オーガニック食材」と、日本の伝統的な健康食の集大成である「マクロビオティック」は、身体だけでなく心も健康になれる料理法です。
バランスの良いオーガニック・マクロビ料理を実践して、美味しく食べて身体の中から健康でキレイになりましょう。
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-5-11
Tel : 03-6715-8772 / fax : 03-6733-8760
Mail:info@g-veggie.com
<引用元>
※1.及川一也著「雑穀」2003年,社団法人農山漁村文化協会
※2.小学館大辞泉「雑穀」
※3.小学館日本大百科全書「雑穀」
※5.古澤典夫著「アワ・ヒエ・キビの絵本」2003年,社団法人農山漁村文化協会
※11.田中雅子著『雑穀をおいしく食べる』2017年,朝日新聞出版
※12.国立情報学研究所「食事療法における地中海食の効果とその展開」
※14.田中雅子著『雑穀をおいしく食べる RECIPE BOOK』2017年, 朝日新聞出版
<参照元>
・小学館日本大百科全書
・平凡社世界大百科事典
・古澤典夫著「アワ・ヒエ・キビの絵本」2003年,社団法人農山漁村文化協会
・及川一也著「雑穀」2003年,社団法人農山漁村文化協会
・小清水裕子著「雑穀・玄米ダイエット」2007年,日東書院
・奈美悦子著「雑穀美」2007年,マイクロマガジン社
https://www.zakkoku.jp/milletdefinition








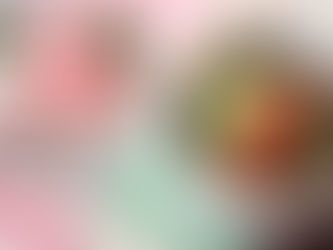









When you pick a development partner for a food delivery app, some key criteria are:
Experience in On-Demand & Delivery AppsMake sure they have built apps with order management, real-time driver tracking, restaurant panels, admin dashboards, etc.
Tech Stack
For mobile: React Native, Flutter, native iOS/Android
Backend: scalable databases (PostgreSQL, MongoDB), cloud (AWS, GCP)
Real-time features: for live order tracking, web-sockets or push notifications
UI/UX Design CapabilityA good user experience is very important for customers, delivery partners, and restaurants.
Payment Gateway IntegrationThey should support secure payments, wallets, multiple payment methods.
Scalability & MaintenancePost-launch support, ability to scale as users grow, handle more restaurants & orders.
Domain UnderstandingUnderstanding how restaurants operate, how delivery logistics work, order surges, etc.
Top Food Delivery…
Grocery delivery app development transforms retail by offering fast, convenient access to groceries from mobile devices. Customers expect intuitive search, real-time inventory, multiple payment options, scheduled or instant delivery, and live driver tracking. A dedicated grocery delivery app development company can deliver an end-to-end solution: user apps, merchant dashboards, delivery rider apps, and a scalable backend with inventory and POS integrations. Key features include personalized recommendations, promo management, subscription options, contactless delivery, and analytics for retention. Security, low-latency performance, and seamless onboarding are essential for user trust. Whether you need a white-label grocery delivery app development service or a custom-built platform, focus on UX, operational efficiency, and last-mile logistics. Choosing the right technology stack, testing for peak loads, and planning…
Grocery delivery app development helps businesses launch a modern, easy-to-use platform where customers can browse products, place orders, and receive groceries at their doorstep. With the rising demand for fast and contactless shopping, brands are investing in feature-rich apps that improve user convenience and increase sales.
A well-built grocery delivery app includes real-time inventory, secure payments, smart search, delivery tracking, push notifications, and multiple delivery options. Businesses can also integrate admin dashboards, analytics, and automated order management to streamline daily operations.
Choosing the right grocery delivery app development company ensures your app is scalable, secure, and customized for your business model—whether it’s single-store, multi-store, or marketplace-based. From UI/UX design to backend development and ongoing maintenance, professional teams deliver complete solutions…
Food delivery app development helps restaurants and startups offer a seamless ordering experience where customers can browse menus, place orders, and track deliveries in real time. With the rapid growth of online food ordering, businesses need robust, user-friendly apps that improve convenience and boost sales.
A high-quality food delivery app includes features like easy onboarding, smart search, multiple payment options, live order tracking, ratings and reviews, promo codes, and push notifications. For businesses, powerful admin dashboards, restaurant panels, driver apps, and automated order management make operations faster and more efficient.
Partnering with an experienced food delivery app development company ensures your app is scalable, secure, and tailored to your business model—whether it's a single restaurant, food chain, or multi-vendor marketplace.…
健康や美容に大いに役立つ雑穀、ぜひ楽しく調理して美味しく食べてみてください! isothermenergy