【オーガニック食材&料理法】秋の味覚を楽しみましょう
- はりまや佳子

- 2015年10月14日
- 読了時間: 4分
更新日:2021年3月27日

秋の味覚を楽しむなら、ちょっとした知識とコツで風邪や肌荒れを予防出来ますよ。
水分たっぷりの秋の味覚を楽しみましょう
晩夏から秋へと季節が移り変わり、澄みわたる青空を眺めているだけでキレイな気持ちになれる素敵な季節がやってきましましたね。
秋は私たちの体の中の「肺」と「大腸」が活発に動き出す時期。 これらの臓器はみずみずしく湿った状態を好む臓器なので、大気が乾燥すればするほど風邪をひきやすく、咳が出たり、のどが痛くなり、声がかれやすくなるので要注意!!
またお肌も乾燥によってトラブルを起こしやすくなりますので、肺や大腸を潤す食べ物を食べて、乾燥から体を守りましょう。 だからといって水を飲みすぎると腎臓が弱って冷えを生じてしまい、肺と大腸を上手に潤すことはできませんので、食べ物の細胞の中に水分をたっぷりと含んだ「秋の味覚」を積極的に召し上がってみてください。
秋おススメの食べ物
穀 物… 玄米・もち 野 菜… 人参、蓮根、大根、濃い緑の野菜の葉(大根の葉・人参の葉) 豆 … 大豆 海 藻… ひじき 魚介類… 小さい海魚(イワシ、ワカサギ) 果 物… りんご、柿、梨
秋は一年のうちで一番お米が美味しい時期!!今年も日本全国で美味しいオーガニック玄米が収穫できたそうですので、圧力鍋や土鍋で玄米ご飯を炊いて、一日の食事の総重量の50~60%いいただき、心と体に強い中心軸をつくって風邪に負けない結構な体をつくってください。
野菜の中で特におすすめなのがレンコン。 レンコンは穴があいていていることから、 「先が見え見通しが良い」と言われ、 昔から縁起の良い食べ物とされています。 また、その形が肺に似ていることがから、 肺を養う食べ物とも言われています。
これからの季節は 「鼻」や「喉」から風邪を引きやすくなりますので、 心や体に不調をと感じた時には、 蓮根のお味噌汁やきんぴらを作って、 いつもよりたくさん噛むようにすると、 体が芯から温まり体調がぐーんとよくなります♪

果物の中でおススメはりんご。りんごは食物繊維やビタミン・ミネラルが豊富で、 昔から「医者いらず」と呼ばれているほどの優秀な果物♪ 日本の食養生法「 マクロビオティック」では、果物の中では、 一番バランスのよいエネルギーをもっているといわれています。
りんごの魅力
抗酸化物質が免疫システムを高め、病気の予防に役立つ
抗酸化物質が肝細胞を攻撃する活性酸素を除去、 肝機能&デトックス効果がアップ
食物繊維が豊富で胃腸の調子をととのえ、コレステロールを低下させる
血液をサラサラにし、心臓を健康に保つ
ポリフェノール」などの抗酸化物質が、酸化ストレスを低減し疲労回復に役立つ
低カロリーな上に食欲を抑制する効果があるのでダイエットに役立つ!
と良いことずくめ!! フルーツ界の女王様といっても過言ではありません。
りんごの食物繊維は果肉よりも皮の部分に多く含まれますので、 皮ごと食べるのがオススメなのですが、 オーガニックではない果物は農薬やワックスがかかっていて、水で洗っただけではなかなか落とすことができないので、 皮を剥いて食べた方が安心です。
皮をむいたら塩水につけておくと、 色をキレイに保つことができる上に陰陽バランスも整うので、 より一層おいしく召し上がれますよ。
それから、りんごは果物の成熟を促す「エチレンガス」を発生させますので、 ほかの果物と野菜とは別々に保存しておくようにしましょう~

秋のお料理のコツ
味つけ … 気温の下降とともに塩気を増やす
調理方法… 焼く、煮る、キンピラ、圧力、長時間の炒め物・煮しめ、プレスサラダ
調味料 … おろし生姜や大根などのピリッと辛いものを食べる回数を増やす
マクロビオティックの味付けの法則は、気温が高ければ高いほど身体を温める陽の力をもつ「塩」を控えて薄味にし、気温が下がれば下がるほど「塩」を増やして食べ物を陽性にする。
そしてこれからの時期は食べ物に「火」という体を温める陽性の要素を加えるために、具材を大きく切り、弱火でじっくり火を入れる調理法で料理するようにします。
また、寒くなってくると体の中の「氣」という生体エネルギーが滞ることで体調を崩しやすくなりやすくなりますので、料理に「おろし生姜」や「大根おろし」などのピリッと辛く、エネルギーを活発に動かす「陰性」の食べ物を加えることで氣の流れがよくなります。
お料理をつくってなんだか味が物足りないと感じたときにはぜひ、「おろし生姜」や「大根おろし」を添えてみてください。特に朝のお味噌汁にいれてみると、心から美味しいと思うに味噌汁に大変身しますよ。
朝は温かいお味噌汁を頂き、心と体を芯から温めて、今日も笑顔で元気に一日を過ごしましょう~

最後まで読んでいただきまして、本当にありがとうございます。それでは今日もお日様のように明るく笑って、お月様のように穏やかな気持ちで楽しい一日をお過ごしくださいね。




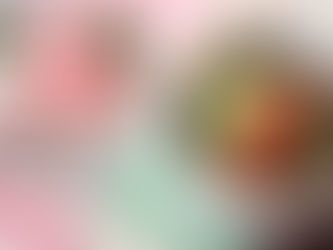













Unblocked Games has been my go-to for quick gaming breaks. The variety of games keeps it exciting, especially during study breaks.
Kaiser OTC benefits provide members with discounts on over-the-counter medications, vitamins, and health essentials, promoting better health management and cost-effective wellness solutions.
Obituaries near me help you find recent death notices, providing information about funeral services, memorials, and tributes for loved ones in your area.
is traveluro legit? Many users have had mixed experiences with the platform, so it's important to read reviews and verify deals before booking.