食品ロス(フードロス)とは?原因・問題点・家庭でできる対策について
- g-veggie

- 2025年6月17日
- 読了時間: 13分
更新日:2025年6月17日

近年、新聞紙面やニュースで「食品ロス(フードロス)」という言葉を目にした方も多いかもしれません。
地球環境の悪化、経済的格差の拡大など、現在私たちが抱えている深刻な問題は少なくありません。食品ロスはまさにこうした諸処の問題とも関連があり、現代人として知っておく必要があります。
食品ロス(フードロス)は社会問題のひとつですが、私たちもまさに今日から、その問題解決のために取り組むことができるのです。
食品ロス問題の原因、実情を熟知しすれば、家庭でできる食品ロス軽減も、より効率的にできるはず。
今日は、食品ロス(フードロス)の問題と向き合ってみましょう。
食品ロス(フードロス)とは
まずは、食品ロス(フードロス)の定義を見てきましょう。
「フードロス」と呼ばれることもある食品ロス。
食品ロスとは、消費者庁によれば「食べることが可能な状態にあるにもかかわらず食品が捨てられてしまうこと」を指します。(※1)
これは、家庭におけるいわゆる残飯だけを指すのではありません。
スーパーマーケットやコンビニなど食品を販売する店や、生産や製造、輸送の工程においても、食べることができる状態の食材が大量に廃棄されているのです。(※1)
こうした食品ロスの現象は、全世界共通の社会問題となっています。
食品ロスによって、食材を生み出すための大事な資源が無駄になってしまうだけではなく、廃棄のためにかかるコストもまた大きな負担となっているためです。(※1)
つまり食品ロスとは、食品を捨てて「もったいない」というシンプルで感情的な理由だけではなく、全世界が手を取り合って解決していかなければならない問題なのです。
食品ロス(フードロス)とSDGsの関連性

食品ロスとセットとなるように耳にするのは、「SDGs」という言葉です。
まずは、SDGsの意味を説明いたします。
SDGsは、世界が2030年までに達成しなくてはならない国際目標のことです。環境と開発に関するこの目標は、日本語では「持続可能な開発目標」と訳されています。
地球の環境を守り、気候変動に心を配り、持続可能な生活や社会を維持するためには、公民の垣根を取り払って取り組む必要があります。SDGsは、世界がこの目標を達成することを目的に、2016年1月に国際連合によって発効されました。(※2)
環境省のサイトには、SDGsに定められた17項目を見ることができます。(※3)
その多くの項目が、食品ロスと関連しています。
「飢餓撲滅」「海洋資源の保全」「陸域生態系や森林の保護」「持続可能な消費と生産」など、食品ロスを減らすことによって状況が改善され、目的を達成できる可能性があるものが少なくありません。(※3)
子どもたちにもわかりやすいよう、消費者庁やユニセフでは「つくる責任、つかう責任、減らす責任」というフレーズを用い、人々の意識を啓発しています。(※1・4)
食品ロス(フードロス)の原因
食品ロスの現象は、具体的にどんな原因で発生するのでしょうか。
まず、家庭の食事情を振り返ってみましょう。
飽食の時代に生きる私たちの周りには、美味しい食べ物があふれています。ついつい買い過ぎて食べきれないまま廃棄してしまうことは、誰にでも経験があることです。そのほか作り過ぎたり食べ残したりという日常的な行為も、食品ロスの原因となります。
私たち消費者には見えない過程でも、食品ロスの原因は数多く存在します。
食べ物を生産する過程では、形が整っていなかったり、過剰に生産して消費しきれなかった多量の食品が廃棄されています。
また外食産業や食料販売店においても、お客さんに渡らないままゴミ箱行きとなる食品は想像以上に多いのです。たとえば、恵方巻など季節のイベントに絡む食材は、その日を過ぎてしまうと見向きもされず、消費期限が切れて廃棄されてしまうわけです。
食品の小売店においては、賞味期限前半3分の2までしか消費者に提供できないという不文律も生きていて、この習慣「3分の1ルール」から多くのフードロスが生まれるという現実があります。(※5)
つまり食品は、生産から消費にいたるあらゆるシーンで、食品ロスの現象が毎日のように発生しているのです。(※1)

食品ロス(フードロス)の現状
身近に存在する食品ロスの問題。
ここで、世界にも目を向けてみましょう。
食品ロスの問題を解決しなくては地球の将来や環境が危ういと実感するために、具体的な数字もあげて説明いたします。
世界の食品ロス
世界中では、どのくらいの食糧が破棄されているのでしょうか?
FAO(国際連合食糧農業機関)が公表したその数字に驚くなかれ。
その量、なんと年間13億トン!
この数字はまた、世界中で生産されている食料の3分の1に該当するというショッキングな現実も報告されているのです。
富める国の人々が食料を大量に廃棄しているいっぽうで、世界には7億人近くが飢えに苦しんでいるといわれています。(※6)全人口の10人に1人は、栄養失調であるという状況が、それを証明しています。(※7)
また、少子化が問題になっている日本とは反対に、世界の人口は現在の79億人から、2050年には90億人に増加するといわれています。
限られた土地や資源から、増え続ける人口を維持するための食料を確保できるのか。大いに危惧されているのです。(※1)
そして食品ロスは、なにも先進国だけの問題ではありません。
開発途上国においても、収穫のための技術不足、輸送手段のためのインフラの欠如、保存設備の不備などの理由で、食品ロスは発生しています。(※7)
食品ロスの状況を改善しなくては、食料を作り出す環境が維持できなくなる可能性が高い。
それが世界の有識者たちの共通した見解であり、まさに今、私たちがその認識を共有する必要があります。
日本の食品ロス
日本のフードロスの数字はどうでしょうか?
政府の発表によれば、2022年に廃棄された食品の量は472万もあったと報告されました。これは、東京ドーム3.8個分に相当し、日本人が1人当たりおにぎり1個を毎日捨てているという重量と合致するそうです。(※7)
国民一人当たりの食品ロス量:
1日約103グラム:(おにぎり約1個分)
食品ロスの内訳(家庭系):
直接廃棄::約102万トン
食べ残し::約100万トン
食品ロスの内訳(事業系):
食品製造業::約117万トン
食品卸売業::約10万トン
食品小売業::約49万トン
外食産業::約60万トン
日本は賞味期限などの安全性に万全を期していることもありますが、見栄えを重視する文化もあるため、規格外となってしまう食品が多いという事情もあるようです。(※8)
さいわいなことに、食品ロスという言葉が普及し社会や家庭での取り組みが功を奏したので、近年食品ロスは減少しつつありますが…
しかし、日本にはこんな深刻な事情もあります。
それは自給率が38%ととても低い、ということです。
ここ数年は、疫病の発生や戦争などの世界情勢が不穏で、食品輸入のための輸送手段も影響を受けることが多くなりました。自給率が低い日本は、こうした事情をもろに受ける食料供給下にあり、すでに品不足や値段の高騰もニュースになっています。
食糧不足や栄養不足はもはや、日本にとっても対岸の火事ではないのです。
輸送費をかけて輸入した食材の多くが食品ロスになっているだけではなく、輸送に費やされた資源も無駄遣いになってしまうという事実にも、目を向ける必要があるかもしれません。(※7)

食品ロス(フードロス)が問題視されている理由
日本には「もったいない」という概念があり、さらに「いただきます」「ごちそうさまでした」という挨拶習慣によって、食を尊ぶ文化があることは喜ばしいことです。
しかし環境問題や貧富の格差など、概念だけでは解決できない問題が、厳然たる事実として存在するのです。(※1・8)
SDGsが提唱した17項目には、直接的に食品ロスに触れられたものはありません。
それではなぜ、食品ロスが世界中で注目され、大きな問題になっているのでしょうか?
それには、以下のような理由があります。(※1)
食品を生産製造する過程でかかるコストが無駄になる
廃棄にコストがかかる
可燃ごみとなった食品の廃棄処理によって二酸化炭素が発生し温暖化が加速する
供給過多によって環境が破壊される(過剰漁獲など)
食を大量に廃棄する富裕国と食が足りない発展途上国との格差が拡大する
こうした問題を体感するために、例を見てみましょう。
和食ブームのおかげで世界では今、日本産の牛肉の需要が高まっています。
それでは、牛一頭を育てるのにはどのくらいのコストがかかるのでしょうか?
農林水産省の統計を参考にすると、牛一頭の飼育にはなんと、66万円強がかかっているのです。(※10)
こうしてお金をかけて大事に育てられた食材が廃棄される食品ロスという現象は、目の前にある食べ物を無駄にするだけではなく、食べ物が消費者の手に渡るまでにかかったエネルギーや人件費も捨てている、ということになるのです。
さらに食品は、ゴミ箱行きになったあとにも環境に悪影響を与えます。
ゴミとなった食品を処分するためのコストは、自治体の大きな負担になっています。
温室効果ガスの多量の排出、灰となって埋め立てられた土壌の汚染など、食品ロスによる問題は枚挙にいとまがないのです。(※8)
食品ロス(フードロス)を減らすために家庭でできること
食品ロスは、環境や将来のために解決しなくてはいけない問題であることが、おわかりいただけたと思います。
国籍や文化の壁を乗り越えて、全世界で取り組まなくてはいけないことはいうまでもないでしょう。
日本国内でもすでに複数の外食産業や食品企業が、食品ロスを目指す試みに着手しています。(※8)
しかし食品ロスの解決のためには、家庭でもできることが多いのです。
消費者庁によれば、一般家庭の収入において食費が占める割合は4分の1。(※1)
にもかかわらず食品ロスが多いという矛盾から脱却するにはどうすればよいのか?
食品ロスの軽減のためにできることをご紹介いたします。
外食する際は適量を注文する
胃袋を刺激されるメニューが多い外食。ついつい、あれもこれもと注文してしまいがちです。
しかし、食べきれなかったそのお料理は廃棄処分の対象になってしまうのです。
外食する際には、過剰に注文しないよう注意することが食品ロスへの第一歩です。(※7)
また近年は、食べきれなかった料理を自宅に持ち帰るドギーバックという容器もあります。ドギーバックを使って食を無駄にしない動きは、世界各地に広がっているのです。
もちろん衛生状態にはじゅうぶんな注意が必要ですが、こうしたアイテムの存在も知っておくと便利です。(※7)
ネットやアプリを活用してフードロス軽減に貢献する
食品ロスをなくすための活動は、インターネットを通じても可能です。
たとえば、賞味期限が近い食品を、それを求める消費者に確実に届けるためのマッチングサイトがあることをご存じでしょうか?(※8)
さまざまな事情で規格から外れてしまったり、市場に出すことができなくても、食べて問題のない食材はたくさんあります。こうした食品を無駄にしないためにも、消費者として食品ロスに貢献するサイトやアプリを使用してみましょう。
買い物は適量、保存は正しく
多忙な現代人である私たちは、自宅で調理して食べる食材も不足しないよう、必要以上に購入してしまう傾向があります。
そうした食品が、冷蔵庫や食品庫に入れたまま賞味期限切れになってしまうというケースも少なくありません。また保存方法が間違っていたため、本来は日持ちするはずの食品を腐らせてしまうという経験をしたかたもいらっしゃるでしょう。
買い物は把握できる量にとどめ、正しく保存し、最後まで美味しく食べる。(※11)
個人で実践するたったこれだけのことが、食品ロスを減らす大きな一歩となるでしょう。

江戸時代は食品ロスゼロ時代
江戸時代の人々は食べ物をとても大切に扱っていたので、食材を余すことなく使い切り食品ロスを最小限に抑える取り組みが、日常的に自然に行われていました。
食品ロスを削減する取り組みとしては、
「食材は必要な分だけ購入する」
「余ったものなどを塩漬け等し長期的に保存する」など。
また江戸時代には自然環境にも配慮されている生活習慣がありました。
「家から持参した容器に豆腐を入れてもらう」
「野菜は風呂敷を使い持ちかえる」など、
包装資材を使用しない生活スタイルでした。
私たちは今こそ、江戸時代の人々の食との向き合い方を学ことで、素敵な解決策がみつかるのではないでしょうか。

あなたのキッチンから食品ロス(フードロス)を実践しましょう!
食品ロスで1世帯年間約65,000円分の食料が廃棄されています。
キッチンは家族の命を育む大切な場所。 食品ロスゼロ料理にチャレンジして、あなたもキッチンから 【もったいない革命】を起こしませんか?

日本のフードロス量(食品ロス量)は年間600万トンを超え、毎日大型10トントラック約1,700台分の食品を廃棄しているのが現状で、これは世界でもトップクラスです。 食品ロスゼロ料理アドバイザー資格認定講座では、日本と世界のフードロス事情と問題点、その解決方法や、全体の40%に及ぶ家庭からのフードロスを削減する調理方法を学ぶ事が出来る資格です。
まとめ
ここ数年、よく目にする言葉「食品ロス(フードロス)」。
食べることを目的に生産したにもかかわらず、廃棄されてしまう現象を指します。
世界的な社会問題となっている食品ロスは、環境や気候の変動、経済格差や食糧不足など、私たちが直面しているさまざまなテーマと複雑に絡み合っています。
食品ロスの意義は理解していても、実際に廃棄されている食品の量を数字で知れば、さらにその深刻さが実感できます。
地球や人類の将来を懸念し、国連が目標に掲げた「SDGs(持続可能な開発目標)」に同調する企業も増えてきました。食品ロスに関しても、すでに多くの外食産業や食品関連の企業が、その削減を目指してプロジェクトを発信しています。
私たちもぜひ、食品ロスを減らすための努力や工夫をしてみましょう。
個人個人でできるこうしたわずかな積み重ねが、地球の環境と未来を守るための大きな力となることはまちがいないのです。
オーガニック・マクロビ料理教室G-veggie

G-veggieはGrain(穀物)とVeggie(野菜)を合わせた造語で、人間にとって大切な2つの食べ物を、料理の中心にして自然に寄りそった生活をしていきたいという意味を込めました。
自然の生命エネルギーあふれる「オーガニック食材」と、日本の伝統的な健康食の集大成である「マクロビオティック」は、身体だけでなく心も健康になれる料理法です。
バランスの良いオーガニック・マクロビ料理を実践して、美味しく食べて身体の中から健康でキレイになりましょう。
【心と身体がキレイになれる】
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-5-11
Tel : 03-6715-8772 / fax : 03-6733-8760
Mail:info@g-veggie.com
※2.小学館日本大百科全書(SDGs)
※5.小学館日本大百科全書「食品ロス」





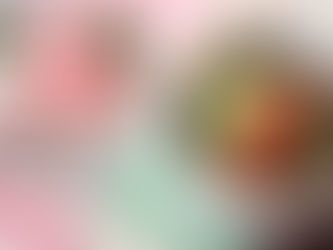












Steamunlocked inspires players to discover more every day.
年間13億トンも捨てられるなんて、マジか!ちょっと待って、うちの冷蔵庫もチェックしないと。Type Soulみたいに、フードロス削減もRanked上位目指して頑張るしかないね!まずは外食でドギーバック使ってみようかな。
Clean energy is always welcome capybara clicker
Loved this post! It’s always inspiring to see creative food journeys. On a different note, for those managing food businesses in Mexico, don’t forget to validar un RFC it’s a key step for staying tax-compliant.
Thank you for the post! For a fun way to unwind, try the New York Times Connections game. If you need assistance, visit our professional word connect solver tool at [Connections Hint Today Answers], your go-to resource for puzzle enthusiasts seeking expert tips and solutions!