リジェネラティブ農業は大地の健全化へのアプローチ!その原理と利点
- g-veggie

- 2023年11月29日
- 読了時間: 10分
更新日:2023年12月8日

地球環境は、これまでにない速さで変化しています。
インフラが整備され優れたテクノロジーを有している日本では、数年前まで、気候変動による大きな災害は年に数えるほどでした。
しかし近年、異常な暑さや局地的なゲリラ豪雨や干ばつなど、人々の生活を圧迫するような現象が頻繁に起こっています。
こうした急激な環境の変化に対処しようと、国際的なレベルでさまざまな試みが行われてきました。
その中のひとつが、「リジェネラティブ農業」です。
日本ではまだ聞きなれないリジェネラティブ農業とは、どのようなものなのでしょうか。
オーガニック食と絡めながら、リジェネラティブ農業について解説します。
1. 食品の増産を求めた結果たどり着いた荒涼たる大地
まず、リジェネラティブ農業という概念が生まれた理由から見ていきましょう。
要因となった現象は、20世紀の食生活と農業にありました。
その理由を詳しく解説します。
「食料不足」への恐怖感が生んだ増産体制
20世紀という時代を振り返ってみましょう。
日本のバブル経済に代表される「所有」への執着は、食べ物にも及びました。
足りなくならないように、とにかく食品を買い貯める。先進国においても「食べ物が足りない」ことが強迫観念のように人びとを追い詰めて、買う、廃棄する、買う、廃棄するという悪循環が生まれてしまったのです。
農産物の生産性を重視する化学農業がメジャーとなったのは、第2次世界大戦後、1940年代以降といわれています。
世界大戦中、食糧不足で苦しんだ日本も、世界のこの流れに乗りました。とにかく農産物を増産するために、化学肥料をどんどん使うことに躊躇しなくなったのです。
化学肥料の大量消費がもたらした環境汚染の数々
農作物の増産を目的に化学肥料を大量に使ったことで、どんな結果になったのでしょうか。
私たちはもちろん、食糧不足からは解放されました。
しかし今度は逆に、生産過剰という問題が生まれました。当然のことながら、環境汚染も深刻化してしまったのです。
化学肥料は人々を飢餓から救う一方で、地下水や土壌の汚染、環境の破壊という負の遺産を私たちに残す結果になったのでした。
こうした反省を踏まえて、欧米各国では早くから、持続可能な環境保全型の農業が注目されていました。
リジェネラティブ農業も、その一環というわけです。

2. リジェネラティブ(環境再生型)農業とは?定義と要素
地球環境保全のために推進されているリジェネラティブ農業とは、具体的にどのようことを行うのでしょうか?
リジェネラティブ農業の定義とともに、4つの目的をご紹介します。
リジェネラティブ農業の定義
リジェネラティブ農業の定義を見てみましょう。
「土壌とそこに生息する多様な生物(有機物)を保護し、農業システムにおける生態系を改善するためのアプローチ」(国連食糧農業機関)(※1)
わかりやすくいえば、農地の土壌を健全に保つだけではなく、本来あるべき姿へ改善し、自然環境を回復させる試み、という感じでしょうか。
化学肥料によって痛めつけられた土壌を、ケアしていく農法といえばわかりやすいかもしれません。
よく耳にする「サステナブル」は、未来の世代に環境悪化による負荷をかけないようにすることが目標です。一方リジェネラティブ農業は、環境への負担を軽減しながら「改善していく」という前向きなアプローチです。
リジェネラティブ農業のための10の要素とは?
国連食糧農業機関(FAO:Food and Agriculture Organization)では、リジェネラティブ農業を構成する10の要素を、次のように定義しています。(※2)
① 多様性
天然資源の安全性を保護強化しつつ、多様化によってエコロジカルな農業を実践する
② 相互協力と知識の共有
研究者や農業の現場にいる人たちの知識を共有し、教育の現場でもその重要性を伝える
③ 相乗効果
食料システムをより効果的に機能させるために、相乗効果システムを構築する
④ 効率向上
最新のテクノロジーを活用し効率を向上させる
⑤ リサイクルの活用
経済的なコストを削減し環境への負荷を抑えるために、リサイクルを活用する
⑥ 環境の回復力の強化
干ばつや洪水、害虫などの被害を受けても回復力がある環境を作る
⑦ 人権及び社会的価値観の見直し
農業従事者への経済的保証や農業促進のために、性別年齢を超えた人材確保と彼らの人権を守る
⑧ 食文化の見直し
社会問題となっている過食や肥満の予防のために、伝統的な食文化を見直す
⑨ 責任あるガバナンスの構築
天然資源の使用や持続可能な農業のための新政策の責任を負うガバナンスを明確にする
⑩ 循環型の経済によって無駄を省く
境界線を省き、循環型の経済を作り出すことで無駄を省く
ひとつひとつが納得できる提言ですね。現代人の1人としてぜひ自覚しておきたいものです。

3. リジェネラティブ農業を実践する世界の試み
毎日のように実感する環境の変化。
悪化する環境の改善のために、リジェネラティブ農業に早急に取り組み、普及させる必要があります。
世界の企業は、どんな形でリジェネラティブ農業に取り組んでいるのでしょうか。
いくつかの例をご紹介します。
アウトドア企業パタゴニア・インターナショナルの試み
リジェネラティブ農業の実践としてまっさきに名前があがるのが、アウトドア企業パタゴニア・インターナショナルの試みです。(※3)
世界食糧農業機関のモットーにもあったように、同社はリジェネラティブ農業を、土壌の恢復という目的だけで行っているわけではありません。
農家の収入の安定や動物福祉も、パタゴニア・インターナショナルがリジェネラティブ農業に踏み切った理由なのだそうです。
パタゴニア・インターナショナルでは、巨大農業は不自然なものであり、すでに崩壊しているという考えのもと、リジェネラティブ農業プロジェクトを開始しました。
同社と提携する150以上の農家は、化学的な殺虫剤や農薬の使用を避け、廃棄される有機物から作る肥料を使用しています。
また土壌を疲弊させないための輪作、土壌の健康を守るための間作、有機物質の多様性を維持するため不耕起を取り入れるなど、実用的な取り組みで注目を浴びています。
こうした取り組みから生産される製品は「変革のコットン」と呼ばれ、世界中から注目を浴びています。
大手企業ネスレもリジェネラティブ農業を支援
パタゴニア・インターナショナル以外にも、数々の大手企業がリジェネラティブ農業を支援する動きが出てきています。
ドリンクや食品の大手企業ネスレもそのひとつです。
ネスレは、2030年には自社製品の原材料の50%を、リジェネラティブ農業から調達することを目標に掲げました。
この目標達成のために、技術支援や投資サポートを強化するとしています。
リジェネラティブ農業を行う農家にだけ重い負担がかからないよう、企業側も経済的精神的なサポートをする、と表明したわけです。
大企業によるリジェネラティブ農業への支援は、今後も増えていくことが期待されています。
日本でも始まった!リジェネラティブ農業をうたった農園
日本のオーガニック市場は、欧米と比べると規模はそれほど大きくありません。
しかし、日本の農業でもすでにリジェネラティブ農法を取り入れるところが出てきました。
そのひとつが、四国にある「阿波ツクヨミファーム」です。
ツクヨミファームのリジェネラティブ農業は、不耕起栽培と混植を根幹にしています。
不耕起栽培を用い、土を耕さず、残った根や虫などの有機物による土壌の改善を図っているそうです。
また、多様な農作物をともに植えることで、それぞれの植物が持つ栄養素が土壌内でミックスされ、改善を促進します。これが、ツクヨミファームが行っている混植です。
混植によって、虫害も防止することが可能ということですからまさに一石二鳥ですね。

4. オーガニックの食を改めて見直そう
リジェネラティブ農業の先にあるもの、それがオーガニックの食です。
オーガニックフードというと、一部の富裕層の酔狂と考える人がいるかもしれません。
しかし実際は、オーガニックとは「土から改善して、そこで健全に育てられたもの」という認識が欧米では一般化しているのです。
「地球に優しく」というモットーも大事ですが、「よい土から生まれた食材は美味しい」と考えるほうが、オーガニック食はより身近に感じられます。
オーガニックフードが通常の食材と比べて割高なのも、リジェネラティブ農業への投資や栽培にかかる手間を考えれば当然、というわけですね。
ここで改めて、オーガニックの食のメリットをまとめてみましょう。
農薬による健康被害の心配がない
安定した食料供給のために、農薬は欠かせないという意見もあります。
しかし農薬の成分には、毒性を示すものも少なくありません。(※6)
農林水産省では、農薬による人体への影響を考慮して、試験や研究を継続し報告しています。
しかしこうした毒性のある成分は、摂取しないに越したことはないのです。
オーガニックの食材は、最初からこのような心配をする必要はありません。
食の安全という観点からみると、オーガニックフードが断然ベターというわけです。
「旬」を実感し、食材の栄養素を摂取
増産型農業により、食材の旬も忘れがちな現代人。
オーガニックの食は、旬を思い出させてくれるのもメリットです。
そもそも旬の食材は美味しいだけではなく、栄養価も高いことで知られています。(※7)
オーガニックの食は、四季に準じて生まれてくる旬の美味を、より豊富な栄養とともに味わえるのがメリット。
お子さんがいる家庭は、食育のためにもぜひ、オーガニックを取り入れたいものです。
食品ロスを減らすことができる
お値段がお高めのオーガニック食材ですが、それが理由で「無駄にできない」と思う方も多いでしょう。
これが「食べ物は無駄にしてはいけない」という良識に直結します。
まだまだ食べられるのに捨てられてしまう食品の量は、日本では年間600万トンに及ぶそうです。(※7)
地球規模で起こっている食品ロス問題に家庭で取り組むためにも、オーガニックの食の選択は大きな力となります。

5.未来の世代に伝えたいリジェネラティブ農業
世界で広がりを見せつつあるリジェネラティブ農業は、さまざまな観点から有効な農法とされています。
第2次世界大戦後に主流となった増産型農業は、私たちに食の大切さを実感する機会を奪ってしまいました。加えて、土壌が枯れていく原因となったのです。
リジェネラティブ農業は、食の健全化のために、今こそ必要なアプローチなのです。
消費者として私自身も、将来の世代への責任を果たす必要があるのではないでしょうか。
リジェネラティブ農業を推進するためにも、家庭から出る食品ロスを減らし、健全な食を選択する。そんな生活スタイルを実践すればきっと、体だけではなく心も健やかになっていくことでしょう。
オーガニック・マクロビ料理教室G-veggie
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-5-11
Tel : 03-6715-8772 / fax : 03-6733-8760
【毎年4月開講】オーガニック料理基礎コース
もっとおうちごはんを楽しみたい
もっと食材の良さを活かした料理がしたい
もっと丁寧に料理と向き合いたい
もっと自分の体調に合った料理を作りたい
もっと地球環境にやさしい暮らしがしたい
もっと家族とのコミュニケーションを大事にしたい
G-veggieは毎日が楽しくなる家庭料理と、
オーガニックなライフスタイルが学べる料理教室です。
オーガニック料理基礎コースを受講していただくと
★心と身体に強い中心軸をつくるオーガニック料理
★自然の生命エネルギー溢れる食材の料理法
★自分の体質や体調に合わせたレシピ
★自然と寄り添うサスティナブルなライフスタイル
を1年間かけて総合的に学ぶことができるので、バランスの良い食生活と、健康的な生活習慣が自然と身につきます。
オーガニック・マクロビ料理教室G-veggieとは?

G-veggieはGrain(穀物)とVeggie(野菜)を合わせた造語で、人間にとって大切な2つの食べ物を、料理の中心にして自然に寄りそった生活をしていきたいという意味を込めました。
自然の生命エネルギーあふれる「オーガニック食材」と、日本の伝統的な健康食の集大成である「マクロビオティック」は、身体だけでなく心も健康になれる料理法です。
バランスの良いオーガニック・マクロビ料理を実践して、美味しく食べて身体の中から健康でキレイになりましょう。
<引用元>
※4.ネスレ日本「再生農業」
<参照元>






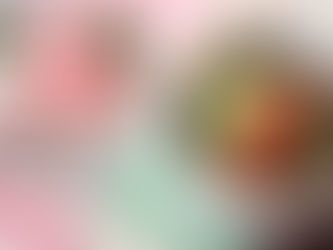












PayPal is one of the most trusted digital payment platforms in the world. It offers fast, secure, and convenient online transactions. To enjoy its features, users must understand the correct PayPal login process. Paypal Login | Paypal Login
素晴らしい体験です。幾何学の経験を積み、才能を最大限に引き出しましょう。このスキルベースのスポーツは、マスターするには大きな挑戦です。Slope Run 様々なテクニカルプログラムに挑戦し、自分自身のスキルを磨いてください。
a
PayPal remains one of the most trusted online payment platforms worldwide. Many users depend on it for secure transactions. However, understanding how to log in safely improves your overall experience. This guide helps you log in smoothly while protecting your account from threats. PayPal Login | PayPal Login
If you like, I can fetch the official Crypto support / troubleshooting page for Web login in India, or guide you with exact steps tailored to your situation (error messages, region). Do you want me to fetch that & send you a link? Crypto.com login issue | Crypto.com login issues