食品添加物って、本当に安全なの?
- はりまや佳子

- 2025年12月12日
- 読了時間: 7分

食品添加物とは?
厚生労働省のHPによると、
食品添加物は、保存料、甘味料、着色料、香料など、食品の製造過程または食品の加工・保存の目的で使用されるものです。
厚生労働省は、食品添加物の安全性について食品安全委員会による評価を受け、人の健康を損なうおそれのない場合に限って、成分の規格や、使用の基準を定めたうえで、使用を認めています。
また、使用が認められた食品添加物についても、国民一人当たりの摂取量を調査するなど、安全の確保に努めています。
と書かれています。
原則として、食品に使用した添加物は、すべて表示しなくてはなりません。
表示は、物質名で記載され、保存料、甘味料等の用途で使用したものについては、その用途名も併記しなければなりません。
表示基準に合致しないものの販売等は禁止されています。
なお、食品に残存しないもの等については、表示が免除されているそうです。
元食品添加物の神様
2011年のことになりますが、オーガニック・マクロビ料理教室G-veggieでは、食品添加物のエキスパート、安部司先生をお招きして講演会を主催したことがありました。
先生は元は食品添加物メーカーのトップセールスマンで、食品添加物の神様とまでいわれた方!
でもご自分のお子さんが自分が携わって開発した食品添加物まみれのミートボールをお誕生日に美味しそうに食べる姿を見て、「こんなものを食べさせてはいけない!」と気がつき、翌日に会社をすっぱりと辞めて、食品添加物の実態をお伝えする人になったそう。
先生が2005年にお書きになった「食品の裏側」は、発売以来70万部以上も売れているベストセラーで、食の安全性が気になる方にはオススメの書籍です。
安部先生の講演会のテーブルにずらりと並んだ「白い粉」の入った容器。さながら実験室の様でした

美味しい「とんこつスープ」の作り方
一通り食品添加物のお話を伺った後、「さて、いまからラーメンスープを作って見せましょう。味は何が良いですか? 私は九州人なのでとんこつ味と行きましょうか」と実演がはじまりました。
そして白い粉のはいった小瓶群から次々と粉をスプーンですくっては、「これが本当のさじ加減ね」なんて冗談を交えながら白い粉たちを調合していきます。
そして最後に、その粉をよく混ぜ合わせて、ポットのお湯を注げば「とんこつスープ」の出来上がり。 使ったのは「白い粉たち」だけで一滴のとんこつスープも混ぜていません。
「さあ、とんこつスープですよ。飲んでみませんか?」
先生がコップを差し出すと、私をはじめ受講生さんたちは一様にぎょっとしたように身を引きましたが、好奇心と勇気あふれる方が恐る恐る飲んでみると…
「おいしい!!とんこつスープの味です。」
と言ったのを聞き、興味深々だった周りの人たちも次々に飲んでみると、
「いつも食べているインスタントラーメンのスープ味と同じ!」
「ホントだ、とんこつスープの味に間違いない!」
と驚きの声が上がりました。 安部先生いわく、このとんこつ味は普段とんこつラーメンを食べなれている九州の人でさえ「おいしい」と唸らせるものだそうです。
一滴のとんこつスープも使わず「白い粉」だけでつくれてしまうとは、食品添加物というのはなんとも不気味なものだと思いました。 ちなみに安部先生はコーラ、レモンスカッシュ、メロンジュースも白い粉だけで作って見せてくださいました。

食べるものは安い方が良い?
平均的日本人の食品添加物の摂取量は1年間でおよそ4㎏、1日平均で11gの食品添加物を食べていると安部先生に講演していただいた当時言われていましたが、最近は7.8㎏まで増えてきたとも聞いています。
食品添加物は天然のものと人工的なものがありますが、人工的な物の原材料は主に石油。
それも原油から私たちが生活に必要なガソリンや灯油などを取り除いたあとの「廃油」と呼ばれる産業廃棄物からつくられているので、原価がとても安いそうです。
食品添加物は食品を腐らないようにして賞味期限を延ばしたり、味を美味しくしたり、キレイな色にして見栄えをよくしたり、膨らましたり、粘らせたりと食品を美味しく、美味しそうに見えるようにする魔法の粉。
質の悪い食材たちも最高に美味しくしてくれるので、日本だけではなく世界中の人々に食されています。
「食べるものは安いほうがいい」
ということを価値の基準とすれば、食品添加物はなくてはならない存在。 そのままでは美味しくない食材に白い粉を混ぜれば、あら不思議、「安くて、賞味期限の長い、美味しい食品」が出来上がるのです
でも安部先生の講演会を聞いた方は全員、
「食べる物は自然のままで、安心、安全なものがいい」と思うようになります。
とはいえ、今の日本で食品添加物ゼロの生活をするのは不可能に近いので、私は食品添加物のないもの(少ないもの)を選ぶことで上質な食生活を実践するように心がけています。

食品添加物を見分ける方法は…
1.食品を買うときに裏の原材料表記を確認する 2./以下に記載されているカタカナやアルファベット、難しい漢字の羅列があれば食品添加物 例)ソルビット・カラメル・アスパルテーム、サッカリン・ph調整剤、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、安息香酸、甘味料、着色料、保存料、乳化剤、酸味料
自分の健康は自分で守る。
そのためには美しくデザインされたパッケージの表で決めるのではなく、裏を見て買う賢い消費者になりたいですね。
オーガニックG-veggeの、

【食品添加物の目利き】になって、スーパーでのお買い物を楽しめる《賢い消費者》になりませんか? 現代日本で食の安全に対して不安を感じている人は6割強以上で、一番気になっているのが「食品添加物」!! 本講座では食品添加物を正しく理解し、自分で食品を選ぶことができる知識を楽しく学んでいただきます。
【こんな人にオススメ】 □食品添加物って実際のところ何なの? と思っている □最近、忙しくて自分で食事を作っていない □ ネットの情報で何を食べて良いのか分からなくなった □ 食品表示ラベルの見方をしっかり覚えたい □家族や子供に出来るだけ安全なものを食べてもらいたい
【講座内容】 1.食品添加物とは 1-1 食品添加物とは 1-2 食品添加物の目的 1-3 食品添加物の種類 2.食品添加物の認定制度 2-1 認証制度 2-2 食品添加物の指定等に関する手続き 2-3 食品添加物の指定等に必要な資料 2-4 主な試験内容 2-5 1日摂取量の推計 2-6 国際的な安全性評価 3.食品添加物の歴史 4.食品添加物の表示方法 5.食品添加物の見分け方 6.食品添加物の課題 7.これだけは避けたい食品添加物 8.食品添加物との付き合い方 8-1 食品添加物フリーの食材はあるの? 8-2 食品添加物を排出する方法 8-3 食品添加物ミニマム生活の秘訣 8-4 オーガニックライフを実践しましょう。
※受講後は日本オーガニックライフ協会より、「食品添加物エキスパート認定書」をお渡しいたします。

最後まで読んでいただきまして、本当にありがとうございました。
それでは今日もお日様のように明るく笑って、お月様のように穏やかな気持ちで楽しい一日をお過ごしくださいね。
はりまや佳子

オーガニック料理研究家
2006年3月に東京都大田区の自宅にてオーガニック料理教室G-veggie(ジィ・ベジィ)を立ち上げる。在籍生徒数は約200名で、北は北海道、南は九州から通っている生徒さんも多数。 2015年2月一般社団法人日本オーガニックライフ協会を設立。マクロビオティックの理論をベースにした、オーガニック料理を提唱し、心と身体がキレイになれる料理とライフスタイルの普及につとめている。
著書:
【心と身体がキレイになれる】
オーガニック・マクロビ料理教室G-veggie
代表 はりまや佳子
〒144-0031 東京都大田区東蒲田2-5-11
Tel : 03-6715-8772 / fax : 03-6733-8760






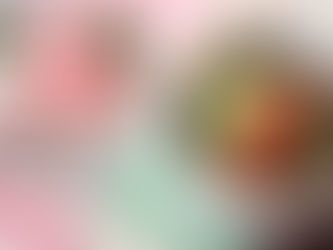













I read your post about the veggie guide and how it breaks down eating more plants in a simple way, and it really helped me think about small steps I can take to eat healthier. One week when school was really busy, I had to do my finance class early in the morning so I could have time to shop and cook fresh meals like these. It reminded me that small habits can make eating well feel easier.
This is one of the best apps I have ever played because Block Blast is super fun and challenging."
CoreChair – Multidirectional Tilt: Dynamic Movement for Back Wellness Experience dynamic movement for back wellness with CoreChair’s multidirectional tilt at https://corechair.com/find-the-best-pelvic-support-chair-to-ease-your-back-problems/. The 14-degree rocking motion facilitates flexion, extension, and rotation, mobilizing stiff joints and strengthening supporting muscles to alleviate chronic pain from uneven spinal loading and prolonged immobility. For functional back issues like muscle tightness or leg discrepancies, it ensures even weight distribution, reducing compensatory shifts that strain the lumbar area. Memorial University’s study confirms participants adopt more upright posture with less back stiffness and enhanced blood flow, combating "sitting disease" symptoms. The tilt stimulates subtle activity, increasing caloric burn by 20% and metabolic demand to support weight management without fatigue. Armrest-free, it keeps elbows at 90 degrees for loose…
The fruits in Suika game have dynamic physics interactions, creating unexpected and sometimes unpredictable combinations. This adds drama and encourages players to experiment with different dropping methods.
Kaiser OTC benefits provide members with discounts on over-the-counter medications, vitamins, and health essentials, promoting better health management and cost-effective wellness solutions.
Obituaries near me help you find recent death notices, providing information about funeral services, memorials, and tributes for loved ones in your area.
is traveluro legit? Many users have had mixed experiences with the platform, so it's important to read reviews and verify deals before booking.